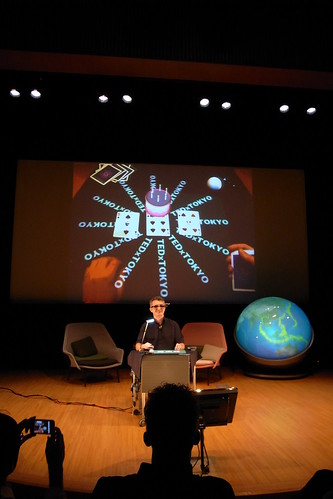「Webデザイン」というのは画面だけのデザインではなく、どちらかといえば長期にわたってじっくり使われるプロダクトデザインの領域に入る。
プロダクトデザインといっても狭義では外形の造形をさすだけのこともあるが、もちろん広義では「いかに人の生活に役立つか」という観点でのトータルなデザインをさす。
投稿者「Atsushi」のアーカイブ
UXBC | Desinging for the Digital Age #2
UX Book Club[UXBookClub.org]のDesigning for the Digital Age読書会に参加。先日6/7の第一回と今回の2回で、700ページもある本書を読破。
初回と今回、共にそれぞれ4時間ほぼ休憩なしの長丁場。
参加メンバーは、浅野さん、ビービット前田さん、深沢さん、IMJ南園さん、SME森本さん、bA奥さん、コンセント西井さん、ハセガワ(+娘)。

Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services
UXBC Tokyo | Designing for the Digital Age #1
IA Instituteから始まった、UX Book Clubの東京セッション。その第2弾のDesigning for the Digital Ageの初回を本日行いました。
浅野さん、ビービットの前田さん、深沢さん、IMJの南園さん、コンセントの西井、長谷川、の合計6人。
今回は、午後2時から6時までみっちり4時間ほぼ休みなくかけて、序章:Getting Started、第一部:Research、第二部:Modelingと、書籍の前半部分を分担して報告しながら議論。
UX Book Clubは、「UXに関する本を読むポータル」として、言ってみれば単に(オンライン上の)場所を提供しているだけなのだが、こういった場所があることで、きっかけが生まれたり、次の読書会のネタができたりするので、意義は大きい。
下記サイトには、スケジュールもあがっているが、当日のレジュメ(というか各自のまとめ)もアップされているので、書籍に興味をもった人は参照してください(参考になるかどうかわかりませんが)。
UX Book Club Tokyo | Designing for the Digital Age
http://uxbookclub.org/doku.php?id=designing_for_the_digital_age
読書会では、実際のユーザーリサーチ、ユーザーモデリング(ペルソナ構築)などのプロジェクトの内容と比較しながら、プロセスの手続きの内容を議論でき、たいへん有意義な時間となった。
面白かったのは、僕が担当したModelingのところで、用いているCodingという分析手法は、Barney GlaserのGrounded Theoryをベースにしていた、というところ。なるほど、そこがつながっていたか。
あと、もう一点、プロジェクトの中で、ユーザー分析をしたりするような人は、インタラクションデザイナ(IxD)として位置づけられていた。具体的には、インタラクションデザイナをジェネレーター(創作担当)とシンセサイザー(理論担当)とに分けて、IxDGとIxDSと呼称していた。一般にIxDSがIAとかぶりがちになる。
いよいよ次回からは、ストーリーボードやプロトタイピングを用いたインタラクションデザイン構築のフェーズに入る。
楽しみ楽しみ。
連塾 JAPAN DEEP 3
去る5/30に開催された、松岡正剛氏による、連塾 JAPAN DEEP 3に参加。
RSWが生みの親である西のTEDと、RSWを日本に紹介した人でもある松岡正剛氏の東の連塾をまとめて受けると、情報量もさることながら好対照ぶりに思うことも多い1週間だった。
ちなみにそれといっしょに、高松で講演したり、札幌でイベントを主催したり、進行中のプロジェクトしたりもあったから、わりと体もしんどい。
さて、今回の連塾だが、松岡さんが萩尾望都氏、松本健一氏、横尾忠則氏がそれぞれ2時間づつの対談をする、という、考えただけで濃いイベントだが、実際内容はかなり濃かった。
それぞれ立ち位置も違う人との対談なので、もう会話の位相が全然ちがっていて、聞いているこちらの頭のモードも90度づつ切り替えながら聞く感じだったので、むしろあんまり頭が馴化されなく、疲れた感じはなかった(少なくともその場では)。
萩尾望都氏、横尾氏の話は、それぞれの作品の裏側と遍歴、おもいのたけを存分に楽しめた。ここまで語らせてしまう松岡さんはやはりすごい、と思わせる。
で、ただ、個人的に頭を揺さぶられたのは松本健一氏との対談。
正直氏の著作は読んだことはなくて、著作の評論とかを読んで(若干偏った)印象を持っていたのだが、すべて払拭され、今年一番の開眼させられたイベントとなった。
話は、松本氏のライフワークとも言える(?)、北一輝研究を題材にしながら、開国から明治〜大正〜昭和の天皇制に対しての当時の人々のピュアな感覚と、「天皇現人神」というシステム(機関)とを導入するに至った思惑とを解体する議論となった。
と書くと、単純化しすぎだが、この話こそまさに、これだけの時間をかけてストーリーを共有しないと得られない理解、と言えるものだった。
おそらくこの回の連塾も書籍化されると思うので、ぜひ読んでもらいたい。
この対談から得た教訓は、知識人に対しての右翼とか左翼とかの安易なレッテルは、その人に対してのこちらがわの思考放棄なのだな、という自戒の念。
と、それはさておき、TEDにしても連塾にしても、個人的にはせっかくこの時代に生きているのに、なんでみんな興味を持たないのかが不思議。
HCD-Netシンポジウムと電子政府ユーザビリティガイドライン
5/28-29に、札幌市にてHCD-Netシンポジウムが開催されました。
HCD-Net|HCD-Netシンポジウム2009
http://www.hcdnet.org/event/seminar/hcd-net_2009.php
TEDxTokyo
去る、5/22に日本初のTEDxとなるTEDxTokyoに参加。
TEDxは米国などで開催されているカンファレンスTEDのローカル版。
TEDx基本的にはTEDとは独立した運営がなされるが、TEDのビデオ素材等は貸与されて、そういったオリジナル素材や独自のスピーカーを呼んで開催されるローカル版TEDといったものとなる。
ローカル版といいながら、会場から、設備から、スピーカーからすべて手がかかっている。
TEDxToktoの模様
http://www.flickr.com/photos/ahaseg/sets/72157618563304921/
特に誘い合ってでかけたわけでもないので、知った人はスピーカーの竹村さん、来場していたnobiさんこと林さん、徳力さん、くらい。
しかしながら、こういったカンファレンスに行くときは、知っている人と行ってしまうとついついそれらの人で固まってしまうので、単身乗り込んだ方がいろいろあって面白い。
具体的なカンファレンスは、まさにTEDな感じでひとり15分程度のショートプレゼンテーションで、各自が「広める価値のあるアイデア(ideas worth spreding)」をプレゼンテーションする。
面白かったのは、以下のあたり:
- Marco Tempest氏のARマジック:ARを使ったカードマジック。ARでこんな応用もあるのか、と感心した。ちなみに、24日のMAKE Meetingでも講演があった模様。
- Barry Schwartz氏の講演(オリジナルTEDのビデオ):仕事をする上での美徳とルールのはなし。インセンティブやルールはものを考えるのをやめさせてしまう。最終的なよりどころは倫理。
- Gunter Pauli氏の講演:Ecover創始者の氏による、ビジネスとして成立するような現実的なエコ事業プラン。
- Renée Byer氏による写真と朗読:ピューリッツァー賞受賞の氏の写真をスライドショーしながら、朗読。なにしろ写真がよい。
- クライマーYuji Hirayama氏による体験談:「最小限のギアで最大規模の結果を残す」というタイトル通り、現代ロッククライミングの肝と、パートナーの大切さがよくわかった。
カンファレンスがすべて英語だったり、全スピーカーのうち日本人が4人だけだったりと、日本で開催されているのに海外カンファレンス的で、帰りに電車に乗ったら成田から帰ってくるような気分だった。
また、英語で話すから口調もポジティブになるから、これが日本語ベースになったときおなじようなテンション、雰囲気が保てるのかどうかは今後の課題。
同じテンションや雰囲気が必要かどうかは議論が必要。
デザイニング・ウェブナビゲーション
James Kalbach氏による「デザイニング・ウェブナビゲーション(原題:Designing Web Navigation)」が刊行されます。

デザイニング・ウェブナビゲーション ―最適なユーザーエクスペリエンスの設計
ハセガワが監訳で携わらせていただいたのですが、白クマ本(Web情報アーキテクチャ)とこの本とで「情報アーキテクチャ」について知っておくべきことが網羅できていると思います。
白クマ本は(特に初版が)図書館情報学的な情報の整理からスタートしているので、Webサイトのある意味で本質である、「ナビゲーション(=リンク)」については手薄でした。
この本では現状、およびこれからのWebサイトで扱われているナビゲーションを機構(メカニズム)、表現型の両面から取り扱っています。
情報アーキテクチャに関わる人におすすめ。
Journal of Information Architecture
独立団体であるREG-iA(Research & Education Group in Information Architecture)が、IA Instituteにスポンサーを受ける形で、Journal of Information Architectureが創刊されました。
Journal of Information Architecture
http://journalofia.org/
Volume 1, Issue 1の内容と、次号のCall for Paperが公開されています。
本誌内容は直接ダウンロード可能となっています。むしろ、紙の雑誌は作らないのかな?
Issue 1, Vol. 1 Spring 2009
- Dorte Madsen Editorial: Shall We Dance?
シャル・ウィ・ダンス? - Gianluca Brugnoli
Connecting the Dots of User Experience
ユーザーエクスペリエンスの「点」をつなぐ - Helena Francke
Towards an Architectural Document Analysis
設計的ドキュメント分析のために - Andrew Hinton
The Machineries of Context
文脈のしくみ - James Kalbach
On Uncertainty in Information Architecture
情報アーキテクチャの不確実性
Call for Paperの内容もいまのIAの問題意識を端的に表しています。
Call for Papers
- Theoretical foundations of information architecture;
情報アーキテクチャの理論的基礎 - Pervasive information architecture;
情報アーキテクチャの普及 - History of information architecture;
情報アーキテクチャの歴史 - Information architecture techniques and best practices; card sorting; freelisting;
情報アーキテクチャ技術およびベストプラクティス:カードソーティング、フリーリスティング - Way-finding in digital environments; human information seeking; human information interaction; navigation and navigation behaviors; findability;
デジタル環境での探索、情報探索、情報のインタラクション、ナビゲーションとナビゲーション行動、ファインダビリティ - Labeling and representation in digital environments;
デジタル環境でのラベリングと表現 - Organization of information; pace layering; taxonomies; folksonomies; collaborative tagging;
情報の組織化、ペースレイヤリング、タクソノミー、フォークソノミー、協調的タグ付け - Social media; social computing; social networks;
ソーシャルメディア、ソーシャルコンピューティング、ソーシャルネットワーキング - Information architecture and digital genres;
情報アーキテクチャとデジタルジャンル - Information architecture development in organizations, in communities, in society, globally;
組織、コミュニティ、社会、世界での情報アーキテクチャ開発 - The role of information architecture in information systems development;
情報システム開発における情報アーキテクチャの役割 - The value of information architecture for organizations;
組織のための情報アーキテクチャの価値 - The impact of information architecture in organizational information policy and information strategy;
組織の情報ポリシーと情報戦略における情報アーキテクチャのインパクト - Multilingual, multicultural information architecture; global information architecture;
多言語、他文化での情報アーキテクチャ、世界的な情報アーキテクチャ - Information architecture design and evaluation for various applications in business, managerial, organizational, educational, social, cultural, and other domains;
ビジネス、経営、組織、教育、社会、文化、などの領域における、情報アーキテクチャ設計と評価のさまざまな応用 - The impact of information, information architecture or information technology on people’s attitude, behavior, performance, perception, and productivity;
情報、情報アーキテクチャあるいは情報技術の、人々の態度、行動、ふるまい、知覚、生産性に対してのインパクト - Information architecture education.
情報アーキテクチャ教育
職種としてのインフォメーションアーキテクトはともかくとして、研究対象分野としての情報アーキテクチャはまだまだ可能性がありそうです。